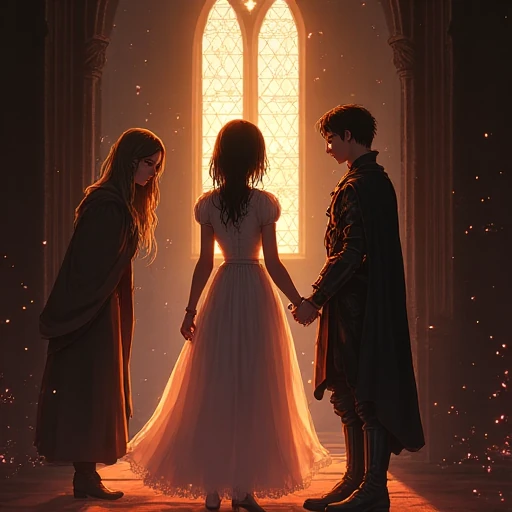「……私がやるわ。モーリスさんの脚を、私が癒やす」
誰よりも静かで、誰よりも確かな声だった。
選定会の会場。候補者たちが華やかに力を披露する中で、彼女だけは、ひっそりと“本物の奇跡”を起こそうとしていた。
それが、転生者フィーア——誰にも正体を明かさず、“聖女であること”をひた隠す少女の物語のはじまりだった。
十夜が贈る『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』は、異世界転生×聖職者ファンタジーという枠に収まらない、優しさと勇気の本質を描いた異色のヒューマンドラマだ。
転生者でありながら、最強の癒しの力を持ちながら、フィーアはそれを声高に叫ばない。
ただ静かに、目の前の傷ついた誰かのために祈る。
それは無自覚の偽善ではなく、自ら選んだ“無名”の道。その姿は、むしろ「大聖女」という肩書よりも崇高で、美しい。
そして、今回の物語でフィーアが対峙するのは、正統派の聖女候補・プリシラ。
彼女もまた、モーリスを助けたいという“真の祈り”を持っていた。
だからこそ、この場面はただの対決ではない。“信仰”と“善意”の重なり合い。どちらが偉いでも、正しいでもない。
読者の心を打つのは、力の優劣ではなく、「誰かを癒したい」と願う想いが交差するその瞬間だ。
物語はフィーアの静かな視点だけではなく、多くのキャラクターの視点から描かれていく。
プリシラの心情、同室オルガの迷い、ザカリーのやらかしとその後始末。そして、300年前の過去編。
それぞれの視点がフィーアという存在を照らし出し、彼女の選択と沈黙の重さを際立たせる。
特にプリシラ視点のエピソードでは、彼女が“聖女候補”という名の下に背負わされた期待と葛藤、フィーアとの出会いを通じて何を感じ取ったかが丁寧に描かれている。
この“他人の目線”こそ、本作の大きな魅力だ。
また、癒しの魔法という一見ファンタジックな要素が、医療や心理ケアに近いリアルさで描かれているのも特徴的。
魔法を乱用することのリスク、回復に必要な“心の安定”、患者と術者の信頼関係……。
それらが作品の根幹にあり、安易な“全回復”で終わらせないのが、本作の誠実さだ。
そして、背景には“選ばれる者”と“選ばれなかった者”の対比が常にある。
それはフィーア自身にも及ぶ。
彼女はかつて聖女として讃えられ、そして命を落とし、転生して“誰にも選ばれない道”を選んだ。
だがその中で、人知れず何人もの命を救い、人の心を照らしていく。
名声がなくても、称号がなくても、ただそこに“本物の聖女”がいる。
この構図が静かに、しかし深く胸に響く。
読後には、余韻が残る。
誰かのために行動するとはどういうことか。自分の信念を貫くとは何か。
物語を読みながら、知らぬ間に自分自身の“在り方”を問い直すような感覚になる。
無料試し読みが可能なサイトも多数あるので、まずは一歩だけ踏み出してほしい:
- 【BOOK☆WALKER】https://bookwalker.jp/
- 【honto】https://honto.jp/
- 【DMMブックス】https://book.dmm.com/
- 【ebookjapan】https://ebookjapan.yahoo.co.jp/
勇ましさも、強さも、きらびやかな魔法もない。
けれど本物の“光”は、静かな想いと、声なき優しさの中にある。
『転生した大聖女は、聖女であることをひた